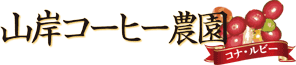農園便り

株式市場が急落するたびに、テレビ・新聞等はヘッジファンドが売りを仕掛けたとワンパターンの解説をする。あれには閉口する。「今、売ってますよー」と言いふらしながら株を売る間抜けなヘッジファンドはないので、どこからそんな情報を仕入れてくるのか不思議だ。ヘッジファンドは情報をあまり公表しないので、彼らの仕業ということにしておけば、誰も検証できない。相場を解説する際に便利なのだろう。
ヘッジファンド業界にいた頃、私の部署では、先物市場に投資するファンドを運用していた。為替・株・債権を始め、商品相場にも投資し、小額だがコーヒー先物市場のポジションもあった。商品相場のトレーダーがコーヒー相場の話をする際に、隔年収穫の話をするのを耳にした。「ブラジルでは今年は豊作だったので、来年は不作で、在庫が減って….」という具合。当時はチンプンカンプンだったが、実際に農夫になると良く分かる。コーヒーは豊作と不作が隔年で生じやすい作物で、生産者には切実な問題だ。
コナコーヒーはアラビカ種ティピカ。味はぴかいちだが、隔年性がひどく、育て難い。コナ以外の産地では香味を犠牲にして、育てやすい品種への植え替えが進でいる。
コーヒーは縦に数本の幹が伸び、そこから横へ枝が伸びる。その横枝に実がなる。そして、一度、実のなった部分には翌年は実らない。その横枝が先に伸び続け、その新たに伸びた部分に翌年、実がなる。つまり、横枝は夏に2つの仕事を同時に行っている。第一に、春に花を咲かせ、8ヶ月かけて実を成熟させる。第二に、横枝をさらに先に成長させ葉を茂らせる。さもなくば翌年は実はならない。この夏の間に、肥料や水が足りないと2つを同時に行うだけの栄養がなくなる。子孫を残すために、果実に優先的に栄養が使われ、葉や枝は枯れる。よって、実の多い年は枝葉に栄養が不足し枯れて、翌年は不作。不作の年は実が少なくて枝や葉に栄養が行き渡って葉が茂るので、そのまた翌年は豊作になる。
コーヒーには大量の水と窒素とカリウムが必要。開花後6~18週間に、果実は水を蓄え大きくなる。夏の盛りの18~30週間後は窒素とカリウムを使い栄養分を蓄える。一方、同時平行して、横枝を伸ばすために窒素が必要。夏場にコーヒーの木の状態を毎日観察し、実と枝と葉の成長具合をみながら、肥料と水の量を調節することが、健康で、おいしいコーヒーを育てるとともに、隔年収穫を防ぐのに必要。
また、5・6月号で紹介したBeaumont-Fukunaga 方式による剪定方法も、隔年性を回避する手段。3年に1度、剪定するので樹勢を常に強く保てる。大量に実をつけた3年目の収穫が終わると樹勢が弱まり、翌年は実がつかないが、剪定してそれを防ぐ。
我々農家にとり隔年性は、かくも一大事だが、喫茶店でコーヒーを飲むたびに隔年性に心を痛める消費者はいない。隔年性は、先物市場でも相場の材料とはなるが、コーヒー相場にさほど影響を与えない。先物市場でリスク回避する大手生産者や中間業者に加えて、ヘッジファンドなどの投資家が市場に参入することで市場の厚みと安定性が増し、色々な事が織り込まれてしまう。生産者の問題は市場が消化し、消費者はそれに煩わされなくても済む。投資家も投機筋も市場効率化を促し、生産者や消費者もその恩恵を受けている。
現役当時、隔年性を語るトレーダーの話を訳が分からずポカンと聞いていた私も、今ではNYへ遊びに行くと、「隔年性を回避するには、夏場の雨量と窒素量がね…」とか「木の剪定方法がね…」などと得意になって説明して、現役連中を煙に巻く。ウォール街の若い連中なんて、目玉に$サインが書いてあるような目つきをしているが、それが?マークに変わっていく。私は市場効率化の撹乱要因か?
≫ 続きを読む
2013/07/02
yamagishicoffee

先月に続き剪定の話。コーヒーの収穫が終わると木を剪定する。剪定には国・地域によって様々な方法がある。コナでは主にBeaumont-Fukunaga Style(以下BF方式)とKona Style(Kona方式)が採用されている。先月、紹介した私の畑の剪定方法はBF方式。コーヒーは列になって植えてあり、3列に1列の割合で、その列の木を全て膝の高さに切る。翌年は隣の列、翌々年はさらに隣の列を剪定し、3年で一巡する。
一方、Kona方式は日系移民時代から行われている手法。一本の木に常に4本の縦の幹を保つ。しかし、それぞれの幹の年齢が異なり、1歳、2歳、3歳、4歳とする。4歳の幹の収穫が最も多いが、収穫後は樹勢が弱まるので、他の3本を残し、それを剪定する。切るとそこから新しい芽が数本出てくるので、最も元気なものを選び伸ばす。
Kona方式 は4本の幹が混み合っている中で、どの幹を切るか一本一本考えながら剪定する。他の元気な幹を傷つけないように小さなノコギリで丁寧に切る。一方、BF方式は一列全ての木の全ての幹を膝の高さで切る。何も考えずに電動ノコギリで次から次へとガンガン切る。熟練度が要求されず、10分の1の時間でできる。
剪定での典型的な間違いは剪定し足りないこと。どの木も頑張って生えているから、切るのは心が痛む。この幹はもう一年いけるかなと、手心を加えて残すと、大抵は失敗する。枯れたり、実が小さかったりする。樹勢が弱いと害虫に襲われる。もったいなくとも、思いっきり切る。心の強さが問われる。Kona方式は一本一本、もったいないという気持ちとの戦い。一方、BF方式は、元気な木も含めて一列全部切るから、実際はこっちのほうがもったいないのだが、最初に決心してしまえば、後は機械的に切るだけで、心が楽。
BF方式では剪定した列(畑の1/3)は、翌年に収穫がないので、Kona方式よりも収穫量は少ない。しかし、常にどこかの列が低く剪定され、空間が生まれるので、両隣の列は風通しが良く、適度に日も当たる。その分、木と木の間隔を狭め、単位面積あたり、より多くの木を植えることで、Kona方式と同等の収穫量も可能。熟練度が要らず、剪定した列はその後、手間も掛からないので、労働コストが下がり、生産性が向上する。
BF方式はEdward Fukunaga氏が同僚のJohn Beaumont氏と1940年代に開発した方式。当時のコナコーヒー農家の8割は日系人。Fukunaga氏は2世で、ハワイ大学の研究員としてコナに常駐し、研究面でのリーダーだった。コーヒー栽培の効率性と品質向上に多大な功績があった。当時コナは生産量は少ないものの、その効率性や品質は世界一で、研究分野では世界を圧倒していた。
ところが、彼の発明したBF方式はコナの日系人の間には、あまり受け入れられなかった。親の代から引き継いだKona方式は熟練と手間がかかるが、それを美徳とし、厭わない日本人気質のせいか、生産量を犠牲にしてまでBF方式に替える人は少なかった。そもそも、昔の畑は列に植えられていないので、BF方式はなじまない。ほとんどの産地のコーヒーの木の寿命は20~30年だが、コナティピカは100年以上も実をつけ続けるので、わざわざBF方式用に列に植え替える人もいない。
Fukunaga氏はその後、中南米に農業指導に行き、BF方式は歓迎され、中南米で広く普及した。彼はコナの仲間の日系人の向上のために研究したのに、逆に他の国の産地に貢献するという皮肉な結果となった。半世紀以上も経った今でも、そのことを根に持って、BF方式を拒絶し、ビールを飲みながら酔っては「Kona方式でなきゃ~ダメだ!」(柳家小三治の酔っ払いの小言を英語でやった感じ)と、くだを巻く日系人の頑固じじいもいる。 コーヒーの味に違いはないんだけどね。
≫ 続きを読む
2013/06/09
yamagishicoffee

コーヒーの収穫が終わると木を剪定する。コナコーヒーはアラビカ種のティピカという種類。ティピカは放っておくと10mもの高さに成長する。昔の日系移民は梯子を使って実を摘んだそうだ。不安定な梯子の上での作業は危険で効率が悪い。おまけに樹勢は弱くなり、実も小さくなる。木の健康を保ちながら、収穫の効率性を高める為に、現在では剪定を行い、高さは3mを越えないようにする。コーヒーの幹は柔軟なので3m程度でも逆U字型にたわませて豆を採ることができる。
剪定には様々な方法があるが、私の畑では全体の3分の1の木を、膝の高さに切る。コーヒーは列になって植えてあるから、ちょうど、3列に1列の割合で、その列を全て剪定する。翌年は隣の列、翌々年は、さらに隣の列を剪定し、3年で一巡する。
コーヒーの木には数本の縦に伸びる幹と、そこから横に伸びる枝がある。コーヒーの実は横枝に生る。剪定すると、1ヶ月で、残った株から縦に伸びる幹の芽が10〜20本出てくる。5月頃、芽が30センチ程に伸びたら5〜6本に間引く。7月頃、60センチ程になったところで、さらに3〜4本に絞る。どれも頑張って成長しているので残してやりたいが、心を鬼にして3〜4本に絞る。将来どの幹と枝がどの空間に伸びていくかを想像しながら、最適の組み合わせを選ぶ。収穫量を優先するならば4本、大きな豆を育てるのを優先するならば3本にする。ここを欲張って5本も6本も残すと、枝が混み合う。日当たりと風通しが悪く、実は全体として小ぶりになる。収穫作業も困難だ。
それぞれの幹から横枝が伸び、1年後の春に花が咲き、その8ヵ月後に収穫となる。剪定した木は1年間、実をつけずに枝と葉と根の成長に栄養を使うので、体力が回復する。剪定して2年後に5キロ程度の実を付け、3年後は20キロほど収穫できる。20キロ(コーヒー300杯分)も実を付けた木は、疲れて樹勢が弱るので、収穫後に剪定となる。写真の手前の木が今年の3月に剪定したもの。奥の右が昨年3月、奥の左が一昨年3月に剪定したものである。
剪定する高さも重要。5年前、コーヒー栽培を始めたばかりの頃、メキシコ人のイケメン、フェルナンドが私の先生だった。初めて剪定をする際に、膝の高さで剪定しろと教わった。低すぎると、低いところから新芽が出てくるので、下のほうの横枝が地面に接する。すると、雑草の処理が難儀となる。地面近くに実が生るため、収穫もひざまづいて膝が痛い。さらに、木の病気の原因になる。地面から蟻が這い上がってきてアブラムシが発生する。蟻とアブラムシは共生関係にあり、アブラムシが蟻に蜜を提供する代わりに、蟻がアブラムシを外敵から保護する。アブラムシが発生すると、黒かびが、枝、葉、実に発生し、木を弱らせる。さらに、人間だって蟻に噛まれたら痛いし、ファイアーアントという蟻に目を噛まれると失明の危険がある。よって、横枝は地面に触れないほうが望ましい。逆に、剪定が高すぎると、木全体が無駄に高くなる。実が高いところにばかり生り、これまた収穫が困難となる。だから、膝の高さがちょうど良い。
ここまでをフェルナンドから教わり、膝の高さで切った。翌日、フェルナンドが来てびっくりして曰く、「膝の高さで切れと言ったのに、低すぎ!」私はすかさず、「だから、膝の高さでしょ」と膝をあてがって反論。すると、メキシコ人でもなるんだ、目がテンに。それを見ていた妻が「あなたの膝はフェルナンドのすね。ももの高さで剪定したら。ハハハハハー」ときた。それはあんまりだろう、いくら彼が若くて、すらっとしたイケメンだからって、そんな言い方。でも、ごもっとも。
≫ 続きを読む
2013/05/01
yamagishicoffee

普段は月に一度しかこのブログは更新しないのですが、高校時代のテニス部のダブルスのパートナーから、私が普段どうやってコーヒーを飲んでいるかを、ここで紹介しろとのリクエストが来たので、番外編を書きます。かつては、毎日毎日、一緒に何キロも走り、泥んこになりながら、腕立てや腹筋を100回以上やった仲ですから、これくらいのリクエストにはお答えします。
一般的に、美味しく淹れるコツは正しい分量を正しい温度で淹れることだそうです。
フレンチプレス
率直に申し上げて、私はコーヒー農家であって、コーヒーの焙煎や淹れ方は全くの素人です。だから、素人でも間違いなく淹れられる方法を使います。それはフレンチプレス(写真左)です。紅茶を淹れる時によく使う器具です。淹れる直前に30gの豆を荒めに挽きます。挽いた豆にフッフッと息を吹きかけて、挽いた豆に混ざっているシルバースキンを吹き飛ばした後、これをフレンチプレスの容器に入れて、上から沸騰したお湯500ccを冷めないうちにゴボゴボと注ぎます。注ぐ前に、容器は温めておきます。4分後に、上からふたを下に押し込み、すぐに全てのコーヒーをカップに注ぎます。マグカップ2杯分です。
シルバースキンは雑味の原因となるので、フレンチプレスに関わらず、どの淹れ方の場合にも、常に吹き飛ばしたほうがよいと思います。シルバースキンとは生豆の周りを覆っている薄い皮で、農家が精製する際にほとんどを取り除くようにします。僅かに残ったものも、焙煎業者が焙煎する際に、ほとんどが焼かれ落ちて、取り除かれます。ただし、焙煎後でも、コーヒー豆の真ん中の縦の割れ目の中に、僅かに残っています。これが、豆を挽いた際に出てきます。だから、挽いた豆に息を吹きかけて飛ばします。ヒラヒラと飛び散ります。
さて、淹れたコーヒーは熱いと味が良く分からないので、ちびちびと飲み、冷めてからの味も確かめます。音を立ててすすって、空気とコーヒーを混ぜて口の中に入れると味が分かりやすくなります。アメリカでは食事中にズルズルと音を立ててすするのはマナー違反なので、ワインのテイスティングの際には上品にほとんど音がしないようにすすります。しかし、コーヒーのカッピング競技では審査員たちは、江戸っ子が蕎麦をすする時の3倍ぐらいの音を立ててすすります。一度、タブーを破ると、歯止めが利かないのか。渋谷ハチ公前でカッピング競技をやったら、審査員がすする度に、騒音表示のパネルの数値が跳ね上がることでしょう。ところで、今でも、あの表示盤はあるのかなあ?
フレンチプレスの特徴は
1)温度が常に一定で、簡単なので当たり外れがない。
2)豆の全ての香味がでるので、その豆の実力を知るのによい。
3)紙や布のフィルターを通していないので、豆の粉が底に残り、舌にザラザラとした感じが残る欠点がある。容器の底に溜まったものはカップには注がないようにする。
ペーパーフィルター
フレンチプレスは全ての味を出しますが、フィルターで淹れると上澄みだけの、いいとこ取りができると言われています。私もペーパーフィルター(写真中央)で淹れることもあります。ところが、下手なので、毎回味が違ってしまいます。20秒蒸らした後に、チョロチョロと熱湯を注いでいくわけですが、私がやると、温度が一定にならないので、当たり外れがあります。
お湯を注ぐとブクブクと泡が浮いてきますが、あくのもとなので、これがろ過されないように注意します。お湯を注ぐ場所を、真ん中に集中させて泡が端へ静かに押し出されるようにします。のの字にお湯をかけて、せっかく端へ押し出された泡をわざわざ潰すのはいけません。こんなことを注意しながら、フィルターの中のお湯の温度が常に95度に保たれるようにするには、かなりコツがいります。漫画タッチの浅倉南のお父さんみたいな人がやれば、美味しいコーヒーができるはずです。上杉達也の淹れたコーヒーは飲みたくありません。南ちゃんのだったら、不味くても飲みたいけど。
コーヒーメーカー
パーティーでは大量に淹れるので、コーヒーメーカー(写真右)を使います。機械が全部自動でやるので、技量が問われず、安定して淹れる事ができる長所があります。しかし、機械だと、お湯の温度が90度以上にならないので、最適な味とはならないそうです。非最適な味を安定的に作ることになります。不味くはないので、それはそれで良いと思います。
家庭用のエスプレッソ器(Moka Pot)を使ったこともありますが、空焚きして、あっという間に壊しました。捨てたので写真なし。
色々書きましたが、コーヒーなんて、所詮、嗜好品ですから、自分の好きな淹れ方で好きな様に飲むことが肝要です。好みの問題ですから、各々が満足していれば、それでいいのです。
≫ 続きを読む
2013/04/21
yamagishicoffee

気候が穏やかなハワイ島の暮らしには大満足だが、桜の季節だけは、日本が羨ましい。ハワイには沖縄から来た寒緋桜はあるが、ソメイヨシノはない。その代わり、昔の日系移民はコーヒーの花が咲くと、畑に出て弁当を使い、酒を飲み、歌い、花見をしたそうだ。コナでは乾季を過ぎて、雨が降り始める2月頃からコーヒーの花が咲く。花は2〜3日で萎むが、雨が降ると、また咲く。これが5月頃まで続く。満開に咲くと、コーヒー畑が白く見える。これをコナスノー(コナの雪)と呼ぶ。
コナスノーになると、どこから来るのか、たくさんのミツバチが現れて蜜を取る。ミツバチのブーンという羽音が、家の中にまで聞こえ、朝、その音で目が覚めるほどだ。一つ一つは小さな羽音でも、それが何万と重なり、コーヒーの葉に反響する。まるでコーヒー畑全体が鳴り響いている感じがする。こういう日は、花を傷めないように、また、ミツバチの邪魔をしないように、農作業は控える。ゴルフに行く良い口実だ
コナコーヒー(アラビカ種)は、同じ花の中で自家受粉するので、必ずしもミツバチは必要ない。しかし、多くの作物は蜂が作柄を左右する。たとえばアーモンド。カリフォルニアが世界の大半を生産している。2月の開花時期に、ハワイを除く全米49州から養蜂業者が集まり、受粉を請け負う。ミツバチは気温が13℃以上、風が時速25km以下で、雨が降っていないという条件が揃うと、蜜を取りに来る。この条件が揃っている時間をBee Hours(蜂時間)という。開花の週、特にピークの3日間にどれだけ蜂時間があったかが勝負で、それによりアーモンド市況が変動する。
ハワイは海を隔ているため、アーモンド受粉に関係のない唯一の州だが、実は養蜂業はとても盛ん。ハワイ島コナといえば、コーヒーやマカデミアナッツが有名だが、世界有数の女王蜂の産地でもあり、各地に女王蜂を輸出している。コナは温暖で、様々な果物がある。1年中、花が咲き乱れる。マウナロア山とフアラライ山が貿易風を遮るので風が穏やか。蜂には住みよい環境だ。
ところが、今年はコーヒー畑に来るミツバチの数が少ないように思われる。世界的なミツバチ減少(蜂群崩壊症候群)の波がハワイ島にも押し寄せている。数年前までは、ハワイは被害のない、世界でも数少ない地域の一つだったが、遂に、減少要因の一つとされるダニとそれに寄生するウィルスのハワイ島への上陸が3年前に確認された。
うちのコーヒー畑の隅にはカボチャが勝手に生えてくる。沢山できると友人に配る。日系人の友人達の間で人気で、山岸農園といえば、コーヒーよりもカボチャだ。コーヒー労働の中心的な担い手のメキシコ人達もこれが好きで、コンデンスミルクで煮詰めて甘いデザートとして食べる。うちは今年も沢山のカボチャが生った。しかし、隣町のワイコロアのカボチャ畑では、ミツバチが来なくて、実が生らなかったそうだ。ウリ科は雄花と雌花があり、受粉には昆虫が必要。そこで、カボチャを育てるために、畑の一角に養蜂箱を置き、まずミツバチを育てることから始めたそうだ。
世界の食料品の8割はミツバチなどの昆虫により受粉されているといわれ、ミツバチの減少は人類文明を覆しかねない由々しき問題。今やミツバチは大切な資源なので、心あるコーヒー農家はそれを守るために、花が咲く直前には、棒を持って畑を歩き回り、くもの巣を取り除く。
今年は、日系移民の真似をしてコナスノーで花見をしてみた。満開の花を眺めながら、暖めたワインに蜂蜜を入れて、雪見酒ならぬ花見酒と洒落込んでいたら、ミツバチが寄ってきて困ったことになった。チクッ。やっぱ、ハチ嫌い。
≫ 続きを読む
2013/04/01
yamagishicoffee

ハワイ島にも雪が降る。スバル天文台のあるマウナケア山(標高4,207m)の頂上は、冬には雪で白くなる。雪が積もると、山頂の薄い酸素の中で午前中にスノーボードで滑り、海まで車で2時間、午後に常夏の海でサーフィンをする強者が現れる。
コナから北へ60kmのワイメアの町は標高が高く、ごく稀に雪が舞う。私はコーヒーを摘みながら、よく落語を聞く。落語は単純作業にもってこい。柳家喬太郎師匠の新作落語に「ハワイの雪」という粋な落語がある。もしかしてワイメアの町が舞台かも。
コナにも少し変わった雪がある。コーヒーの収穫は秋に始まる。年を越す頃には収穫も終盤。8割方の実は既に摘み取られている。コーヒーの木は残った実に栄養を与えようと、栄養分を枝や葉から実に移動する。葉は黄色くなる。この時期コナは乾季で、幹や枝や葉は乾燥し、コーヒーの木は最後の力を振り絞っているように見える。家内などは「頑張れ、もう少しだからね」などと、木に話しかけながら実を摘んでいく。1月、収穫が終わる頃になると乾燥は進む。コーヒーの木は成長を止め、冬眠したようになる。
やがて、春が来る。雨が戻ってくる。雨が降る度に、コーヒーの木は水分を蓄える。同時に日照時間が長くなり、気温が上がると、木は成長を再開する。緑の新芽が芽吹き、木は元気を取り戻す。そして、雨の数日後にいっせいに白い花を咲かせる。花の命は短く、2〜3日ほどで萎れてしまうが、次の雨が来るとまた咲く。これが5月頃まで何度も繰り返えされる。その中でも、特に満開に咲くと、コーヒーの木も畑全体も白く見える。まるで雪が降ったように見えることから、これをコナスノー(コナの雪)と呼ぶ。
コナスノーになると畑いっぱいにジャスミンの様な甘く芳しい香りがする。コーヒーはガーデニアの仲間。うちの垣根のクチナシと同類。クチナシは学名がGardenia jasminoidesで、意味はジャスミンのようなガーデニア。この仲間はジャスミンとは親戚ではないが、香りはジャスミンに似ているらしい。
コーヒーは開花後1ヶ月程で、花が散った跡に小さな緑色の実がなり始め、3ヶ月で小指の先ぐらいに成長する。その後サイズは変わらないが、中に徐々に栄養を蓄えて、8ヵ月後には赤く熟す。花は2月から5月にかけて咲くので、収穫は10月から1月。
このスケジュールは場所によって異なる。コナコーヒーの産地は標高200mから800m。標高の低い地域は、日差しが強いので、成熟に要する期間が短い。豆は小粒で酸味が強い。標高が上がるほど、山腹の雲が厚くなる。雨量が多いから豆は大きくなる。日差しが柔らかいから、ゆっくり成熟し、甘みが増す。この狭いコーヒー産地の中で、同じコナティピカの品種を栽培しても、標高や場所により、気温、雨量、晴天率などが異なり、微妙に異なったコーヒーが産まれる。他の畑と混らない小規模経営のエステートコーヒーだと、それぞれの違いを楽しむことができる。
年によっても成熟の時期は異なる。収穫は、通常、4ヶ月かけて畑を5周ぐらいするが、今シーズンはコナ全体が11月に一斉に赤く熟した。11月一発勝負の畑もあったらしい。時期が集中しすぎて、労働者が足りず、樹上で実を腐らせた農園が続出した。数年前には逆に、11月の収穫が少なく、10月と12月に収穫が集中した。11月分は8ヶ月前の花が咲いた日に豪雨が降り、長雨をいたずらに、眺めているうちに、花が落ちてしまった。
「花の色は うつりにけりな いたづらに わが実地に降る ながめせしまに」
今年のコナスノーは穏やかな天候をになることを願う。
(注):百人一首の小野小町の歌は「花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに」
≫ 続きを読む
2013/03/01
yamagishicoffee

1年前にトラックを購入。本物の農家になった気がして誇らしい。トヨタTacoma。四輪駆動で畑の斜面も大丈夫。夕方、その日に摘んだ実を45kgの麻袋に入れて精製所へ運ぶ。以前はNY時代からの愛車ベンツのトランクに入れて運んだ。しかし、麻袋から果汁が染み出るし、雨の日の収穫は摘んだ実も麻袋もずぶぬれ。ビショビショのままトランクに入れるのは抵抗があった。実際、乗用車に麻袋を載せる人はなく、ましてやベンツだと”Nice truck!”とからかわれた。
コナの道路には所々に「ロバに注意」の標識がある。多数の野性化したロバがいる。昔、コーヒー農家はロバを飼っていた。収穫したコーヒーを麻袋に入れ、ロバの背中に2〜3袋を載せて運んだ。トラックのない時代、ロバは重要な戦力で、随分こき使われた。牛や馬より丈夫で粗食に耐え低コスト。道端の草だけで餌はやらない。空腹と疲労で動かなくなることもしばしば。ロバは頑固。こうなると埒が明かない。餌を鼻先に差し出しながら誘導した。
また、古い本によると、コーヒー豆の劣化の要因の1つにロバの汗とある。かわいそうに、重たい荷物を運び、大汗をかく。すると、豆に匂いが付いた。山岸コーヒーは私ども夫婦の汗と涙の味がするが、ロバの汗は駄目らしい。
1日を終え、疲労困憊のロバを、今度は農家の子供たちが待ち構えた。背中に乗ってレースをして遊び、親に叱られたそうだ。私の幼稚園時代ロバといえば、「おはよう!こどもショー」で愛川欽也が着ぐるみに入っていた「ロバくん」。ロバは世代を超えて人気者。そういえば、私が中学生の頃、ラジオの深夜放送(パックインミュージック)で愛川欽也さんが「ロバくん」の着ぐるみは汗だくで大変だったと語っていた。やっぱりロバは汗っかき。
コナではロバをコナ・ナイチンゲールと呼ぶ。看護婦ではない。ナイチンゲールとは夜に鳴く鳥で、夜鳴きウグイスと訳す。ロバは大切な輸送手段だが、昔の貧しい日系人農家では一家に一頭しか飼えない。ロバはひとりで寂しいので、夜になると大声で近所のロバと鳴き合った。そこでコナ・ナイチンゲールとあだ名された。
戦時中、ハワイに多数の兵士が駐屯した。戦後、軍隊が本土に撤収する際に、多くのジープが払い下げられた。コーヒー農家は廉価でジープを購入し、生産性が飛躍的に向上した。不要となったロバは捨てられ野生化し、今に至る。色の黒いロバは夜は見づらい。道に出てきたロバと車が衝突する事故がたまに起きる。「ロバに注意」だ。
さて、コナのコーヒー産地はフアラライ山麓の標高200m〜800m。その中央、標高500m近辺にママラホア・ハイウェーが走る。ハイウェー(高速道路)とは名ばかりで、昔、ロバが通った狭い道だ。今でも、コーヒー畑はこの道の左右(山側と海側)に広がる。かつて、ロバの鳴き声が響き渡ったこの辺りは、コーヒー畑の合間に、Imin Center(移民センター)、旧日本語学校、日本式墓地、Komo Store(広島県出身河面家)やKimura Store(山口県出身木村家)など日本人町の名残の風景が続く。かつてはコーヒー農家の8割が日本人。この道は現代の日本人にも観光ルートとして面白い。
ただし、この道は走りづらい。狭く斜面を蛇行する道は視界が悪い。少しでも道を逸れると坂の下のコーヒー畑に転落する危険がある。たまに、カーブの向こうから突然、こっちの車線に対向車が現れる。たいていは日本からの観光客だ。かつての日本人町といえども、ここはアメリカ。間違えずに右車線を走って貰いたい。「ロバに注意」の標識もいいが、「日本人観光客に注意」の標識も作ってもらいたいものだ。
かく云う私も20数年前、渡米直後にNYで一番大きな高速道路(I−95)を、間違って出口から入って逆走したことがある。普通は高速道路に入ると前の車のテールランプが見えるものだが、このときはヘッドライトがたくさん。しかも、猛スピードで近づいてくるからビックリした。よく助かったと思う。
≫ 続きを読む
2013/02/01
yamagishicoffee

邦銀に勤めていた若い頃、上司にカラオケ好きがいて、金曜日ともなると朝の5時までお供した。歌が下手なので正直つらかった。それに、素人の下手な歌を我慢して聞く上、褒めちぎらねばならぬ。迷惑な話だ。我慢して聞いている分には恥をかかずに済むので隅で目立たぬようにしていると、「君も歌いなさい」と順番が回ってくる。万事休す。だが、こっちもサラリーマンの端くれ、固辞して座を白けさせる訳にはいかない。勇気を出して歌うのだが、不思議なもので、歌っているうちに、だんだん気持ちがよくなる。仕舞には、ネクタイを頭に巻いて大騒ぎ。朝まで調子外れに歌いまくり、他人に大迷惑を掛ける側に回る羽目になる。あれはよくない。
「流れくる 若き唄声 コナ休暇」コナの図書館でこの句を見つけた。かつて(1932〜1969年)コナの小中高校では、コーヒーの収穫に合わせて、9〜11月を夏休みとしていた。ハワイでもコナだけ。これをコナ休暇と呼び、子供は大人に混じってコーヒー畑で働いた。この句は、家族総出の厳しい農作業を楽しくする為に歌を歌った光景を詠んでいる。たしかに、現在80歳以上の日系三世たちは、日本の古い歌や民謡、童謡、演歌をよく知っている。両親・祖父母から畑で習ったそうだ。先日、日系人のクリスマスパーティーに招かれた。興がのると、ウクレレが登場し、昔コーヒー畑で歌った歌を老人たちが懐かしそうに歌う。中にはパパイアやココナッツの登場するハワイ風にアレンジした、へんてこな替え歌もある。若い世代は「何これ?」と首を傾げるが、歌っている当人たちは大笑いで、昔話をしながら盛り上がる。さらには90歳の長老から「もっと、テンポ速く歌わないと速くコーヒーもげないぞ」と日本語で野次が飛んだりする。
時を経て、日系人は社会進出を果たし、生活をコーヒーのみに頼らずとも良くなった。児童福祉法の観点からコナ休暇は廃止され、日系人の家族総出の作業は消えていった。現代の収穫はメキシコや中南米の労働者が中心。普段、米国本土で働いている彼らは、冬の収穫時期になるとコナに来る。そうやって食い繋いでいる。中には哲学者風に真面目な顔で摘んでいる人もいれば、陽気に仲間を笑わせながら摘んでいる人もいる。時折、スペイン語の歌声が聞こえてくる。畑のこっちから若者が1小節歌うと、向こうからそれを受けて、誰かが、また1小節続ける。そして、ゲラゲラ笑い、陽気に収穫作業が進行する。私にはチンプンカンプンだが、スペイン語の分かる家内によると、あの女の子が可愛いとか、いやいや、あっちの子の方が可愛い、など知り合いの女性たちの噂話を替え歌で唄っているのだそうだ。「僕の心を奪っていったー♪」さすがラテン系だ。
NHK紅白での美輪明宏「ヨイトマケの唄」は圧巻だったが、労働者の歌は日本に残っているのだろうか。日本人は何百年もの間、田植えや稲刈りの合間に歌ってきた。炭鉱や金山にも歌があった。民謡の起源だ。ところが現代は、耕運機やコンバインによる作業では一人でドドドドドーとエンジン音を聞いているうちに終了。皆で歌う暇などない。自動車工場のラインで歌に合わせて自動車を組み立てているとは思えない。丸の内のオフィスで業務中に「サラリーマンは気楽な稼業ときたもんだ〜」と植木等のように歌ったら、たとえ上司がその通りと納得していても、一応、叱られるだろう。
効率化、ハイテク化が進むにつれ、労働の場から歌は消えていった。歌を失った我々は、代わりに仕事帰りにカラオケに通うこととなった。カラオケこそ田植え歌の嫡流だ。だから、手ぬぐいの代わりにネクタイを頭に巻いて歌うのだ。
≫ 続きを読む
2013/01/10
yamagishicoffee

今年の大リーグのプレーオフにボルティモア・オリオールズが進出した。同球団は1900年よりサヨナラヒットでの負けなしという記録を持っていたが、ヤンキーズとのプレーオフ第3戦で記録が途切れた。ヤ軍は黒田が9回まで好投。1点差を追う9回、ヤ軍のジラルディー監督は、なんと大リーグ年俸1位の主砲ロドリゲスに替えて代打を送った。40歳ベテランのイバネスである。采配が的中。彼が同点ホームラン。延長12回に彼が再びホームランを放ち、オリオールズは112年ぶりにサヨナラ負けを喫した。
さて、コナコーヒーは今では希少なティピカ種(アラビカ種ティピカ)。数ある品種の中で、最高の香味を持つが、栽培・収穫に手間が掛かり、生産性が低いのが難点。樹高が高く収穫が困難。剪定しないと3メートルを超え、台に乗って収穫することもある。病気に弱い上に、直射日光にも弱い。世界的には1960年代以降、品種改良により、樹高が低く収穫が容易で、直射日光に強く日陰樹のいらない新種コーヒーが植えられた。やがて、各地でティピカは姿を消した。一方、コナは毎日午後は曇るので日陰樹が不要。昔ながらのティピカを昔ながらの方法で収穫している。これが幸いし、コナはティピカの甘いさわやかな酸味を守る最高級品としての地位を確立した。
ティピカは最も原種に近い種類。市場に出回る品種のほとんどがティピカを改良したものだが、香味で本家ティピカに勝るものはない。品種改良は香味を犠牲にし、生産性を優先した。香味のための品種改良がなされないのがコーヒー業界の不思議だ。
中南米では、かつては大木の日陰にコーヒーを植えていた。60年代の直射日光に強い品種の登場以降、森を切り開き、広い平地に、これを植えた。化学肥料と農薬を大量に使用し、生産性が飛躍的に向上した。いわゆる緑の革命のコーヒー版だ。しかし、この結果、90年代に入り、アメリカで渡り鳥の減少が明らかになった。
ボルティモア・オリオールズの名前は本拠地メリーランド州の州鳥のオリオール(ムクドリモドキ)からきている。この渡り鳥は冬の間は中南米のコーヒー畑の日陰樹の森へ移住する。ところが、森林伐採、農薬乱用で、渡り鳥の住む場所がなくなり数が減った。森林伐採によるコーヒー生産を批判する環境保護団体にとってオリオールは象徴となった。アメリカでは近年、日陰樹による栽培の促進を擁護する消費者意識を高める為に、鳥に優しいコーヒー(Bird friendly coffee)なる認証を付けたコーヒーが登場している。
人類による環境破壊や気候変動は困った問題だ。先日、大型台風サンディーが米国東海岸を襲った。英語でサンディー(Sandy/Sandie)とは、ゴルフでバンカーから脱出してパーを取る事を意味する。私には心の友だ。しかし、今回のサンディーは猛威を振るった。私がハワイへの移住直前に一時期住んでいたマンションが浸水した。かつての住居が水没するのをテレビ中継で見て、引越した後でよかったと胸をなでおろした。すると、知人から電話が来た。NY地区で販売中の私のコーヒーを保管するブルックリンの倉庫も海からの高波に浸水した。あんなに愛情いっぱいに育て、丹念に摘んだ私たちのコーヒーの生豆は海水に漬かり全滅した。
捨てるしかない。塩味の効いたコーヒーなんて誰も買わない。「この磯の香りがたまらないね」なんて誰も言ってはくれない。温暖化を呪った。サンディーを恨んだ。でも、あまり恨んでばかりでは健康に悪いので、気晴らしにゴルフに行ってみた。珍しくバンカーからパーを取り、そのときに思った。やっぱりサンディー好き。
≫ 続きを読む
2012/12/02
yamagishicoffee

旨いコーヒーを育てるには何が大切か。木の種類、気候、土壌など色々の条件がある。これらはどこの土地に、どの種類のコーヒー畑を植えるかで、ほぼ勝負がつく。しかし、これ以外にも、我々の日々の作業が味の違いを生む。それは赤い熟した実だけを摘むこと。この単純なことが非常に難しい。
コナでは春にコーヒーの花が咲く。開花後1ヶ月ほどで小さな緑色の実がなり、徐々に大きくなる。7ヶ月を過ぎると黄色やオレンジに色づき、約8ヶ月で赤く完熟する。花は1月から5月までバラバラと咲くので、収穫は9月から1月。収穫時にはひとつの枝に緑の実(未熟)と赤い実(完熟)とが混在する。その中から赤い実だけを摘む。ひとつひとつ手で摘む作業はかなりの注意を要する。3週間で農園を一周して元の木に戻ると、前回、黄色く熟し始めた豆が、その間に赤く熟し、摘み頃となっている。収穫時期に農園を7〜8周する。1周に5週間以上かかると、完熟を通り過ぎて乾燥したり、腐敗したりする。これは腐敗臭などの雑味が入る。逆に急ぎすぎると、摘み方が雑になり、緑の豆が混入する。これが入ると渋みがでる。クリーンな味を出すには写真のAからBまでの色の実を摘む必要がある。A以下は摘むには早すぎで、B以上は遅すぎ。
さて、世界中のほとんどのコーヒー農園では労働者(ピッカー:摘む人)を雇いコーヒーを摘む。農園主は赤い実だけを摘むよう指示するが、徹底するのは至難の業。ピッカーは摘んだ実の重さで支払われる。たくさん摘めば儲かる。だから速く摘む。どうしたって緑の実が混じる。彼らだってそれで生活しているのだから仕方がない。
テレビや雑誌で、「この農園では赤い実だけを摘んでいる」と赤い実がバスケット一杯に入っている映像を見かけるが、はなはだ疑問だ。取材陣が来れば、ピッカーだって2〜3日の間は我慢して赤い実だけを摘むだろう。しかし、集中力は長くは続かない。5ヶ月間、毎日10時間も摘むわけだから、いつも取材陣がいる時と同じようには摘めない。それが人間というものだ。まして、日本人は言われたことを実直に長時間にわたって行う忍耐力が高いが、多くの国はそれを美徳とは思っていない。漫画「巨人の星」世代の私はド根性で摘んでいるが、そもそも「根性」なんて単語は英語には訳せない。そんな概念がない。だからピッカーに完璧を強要するのは難しい。うるさく強要すれば、強要しない隣の農場にピッカーが流れるだけだ。
幸い我々は小規模なので、あまりピッカーを雇わずにやってこれた。実直に赤だけを摘む。しかし、どんなに丁寧に摘んでも、緑の実は混入する。だから、摘んだ実は平らなところに広げて、好ましくない実を取り除く。一時間に10分ぐらいはこの作業をする。効率は落ちるが、品質を保つには欠かせない工程だ。
一日10時間、シーズンに合計1千万回以上、赤を摘む。赤、赤、赤、そして、また赤。単純作業の繰り返し。こうなると、チャップリンの映画「モダンタイムズ」状態。頭と体が止まらない。異常に赤に敏感になっているので、赤く丸いものは何でも摘みたくなる。町のスーパーで火災警報器の赤いボタンを見ると、思わず飛びついて摘みたくなるから危険だ。これまでは、この条件反射的な衝動を理性が押しとどめてきたが、今年はやるかも。
≫ 続きを読む
2012/11/10
yamagishicoffee