雑誌「珈琲と文化」1月号の拙稿を転載します。ご笑覧ください。
ついに寅年。とうとう還暦となってしまった。
人生を振り返ると情けない。大学では学問などはせず、ただ就職に有利だから「優」を並べた。就職後は、良い役職に付きたいから社内の米国MBA留学に応募した。MBA取得後は、最先端の仕事をしたいとNY支店を希望。さらに、三十五歳で米国金融機関のNY本社へ転職し、社内で新たな事業を立ち上げた。すごい競争社会だった。生き残るために必死で働いた。成果を出せば出すほど昇給・昇進した。アメリカ社会が世界中から優秀な人材を集める魔力だ。高揚感に我を忘れて猛烈に働いた。運も良かった。自分でも驚くほどの力を発揮し、得意になって重責を負った。
そして厄年。四十二歳の時、突如、癌を告知された。手術は痛かった。
バカバカしくなった。日本の教育制度に乗ったら、阿呆なレールに乗っていた。受験、就職、留学、転職、昇進と通過して癌手術に到着。幸いお金だけは貯まったが、使う前に死んだら元も子もない。このレールから降りなくちゃ。
ここまで育てたビジネスとグループを捨てるのは辛かったが、二年かけて体制を整え四十四歳でリタイアした。リタイアといえば聞こえは良いが、ポートフォリオマネージメントどころか、自分の健康マネージメントもできず、競争社会の魔力に引き込まれ、そして弾き飛ばされた。
妻は弁護士としてヘッジファンドのパートナーで忙しかったので、彼女がリタイアできたのは一年後。私は一年間、ひとりでリタイア生活を満喫した。
十二月の退職の日、会社の帰りにキャンディーズのCDを買った。翌日、それをガンガンかけながら車でNYからフロリダのオーランドへ向かった。「もうすぐはーるですねえ♪」。雪のNYから南下すると、徐々に暖かくなる。ワシントンDCを過ぎるとコートを脱ぎ、二日目、ジョージアでセーターを脱ぎ、三日後にフロリダに着くころには長袖がTシャツに代わった。極寒のNYでストレスだらけだった身も心も徐々に温まっていった。
ハンデが0になるまでゴルフをする。当面の目標だった。オーランドにアパートを借り、ゲーリー・プレーヤーなど多くのプロを育てた有名コーチのフィル・リトソン氏に付き、練習の日々が始まった。多くのツアープロが冬にオーランドで練習をする。一緒に練習した。毎日、千球はボールを打った。うれしくて止まらない。なにせリタイアしたばかり。
ゴルフなんてプロと同じように練習すれば、数ヶ月でハンデが0になると思っていた。ところが向こうは二十歳代、こちらは四十半ば。すぐに手首と十本の指が腱鞘炎になった。ゴルフどころかグーが握れない。無理してグーにすると中指だけが曲がらずに伸びたままで、アメリカでは非常に都合の悪い状態となった。
そこで考えたのが基礎体力の向上。ミッシェル・ウィー選手らのトレーナーのダグ・パラ氏のもとでストレッチ、筋力強化に励んだ。ところが今度は股関節が動かなくなった。医者の診断ではストレッチとウェートトレーニングのやり過ぎ。処方された消炎剤を飲んだところ、今度は血圧が異常に上がり、服用を断念。若い韓国の女子プロに囲まれた夢のような生活は危機に瀕した。遂に、NYで働く妻から「いい加減にしなさい」とダメだしを喰らい、NYへ逆戻り。たった半年でゴルフからも弾き飛ばされた。
もっとスローダウンしなければ。翌年、妻が無事にリタイアしたので、もっとリラックスした雰囲気でゴルフとスキューバダイビングのできるハワイ島に流れ着いた。
たまたま買った家にコーヒー畑が付いていた。生まれも育ちも東京。仕事はNY。農業の事は何も知らなかったが、一つの理想形として、チャップリンの映画「モダンタイムス」で、窓から果物を採り牛乳を搾る田舎家の生活をチャップリンと少女が夢見るシーンが印象に残っていた。名曲「スマイル」が流れるあのシーンだ。そういえば、癌の手術後に初めて出勤した、その帰りの車の中でNat King Coleの「スマイル」を何十回もかけながら運転したっけ。そんなスローライフに憧れる感覚で、コーヒー栽培を始めた。
見よう見まねでコーヒーを摘んでみたが、隣で摘むピッカーとは大違い。さすがにプロは速い。感心した。同じくらい速く摘めるようになりたい。毎日十時間、コーヒー摘みに励んだ。周りから、そんなにがむしゃらに働いたら体を壊すよと忠告された。お百姓さんって怠け者だなあと思った。でも、彼らは正しかった。またもや、指が腱鞘炎になった。フロリダで痛めた指は、酷使するとぶり返す。農家の人はなんだかボーっとしているように見えるが、彼らは疲れない体の動かし方やペースを知っているのだ。
コナで日系人のゴルフグループに出会った。リタイアした日系三世中心の三十人ぐらいのグループ。中には九十歳代の人もいて、私は最年少。三世の彼らは、明治期に移民した祖父母の薫陶を受け、大いに慕っている。道徳心に富み、ずるい行為を戒め、他人を気遣い、地域社会へ貢献する事を旨とする。まるで、明治の日本が保存されている。
貧しいコーヒー農家出身。戦中戦後の厳しい時代を生きた彼ら自身は、教師、医師、大学教授、消防士、会社員などを務め貧困から抜け出た。多くが「体を壊すから、コーヒー摘みは、金輪際ごめんだ」と笑い飛ばす。とにかく元気で、よく遊び、よく笑い、日本食を食べ、コナコーヒーを飲む。ハワイの日系人が全米で最長寿なのも納得できる。
私がコーヒー畑を始めた頃、肥料の撒き方を教わった。肥料は季節や雨量や実の成長具合により、最適な成分をタイミングよく施す必要があり、なかなか奥が深い。長年の経験に基づくアドバイスは実に適切。しかし、それを実践しているのか尋ねたら、返ってきた答えが、「冗談じゃない。肥料なんて手間と金がかかる。さらに困ったことに、肥料をやると秋に沢山の実が生るから、摘むのに手間隙がかかって、ゴルフの時間が減る。人生はもっと楽しまなくちゃ」。人生の極意を教わった。
彼らに限らず、ハワイの農家は、自分の身体だけではなく、植物に対しても、気象条件や自然に合わせて、無理のないように作物に接している。
ナスは夏野菜だと思っていた。日本の園芸店でナスの種を買ってきた。夏に美味しいナスが採れた。苗は元気そうだから、水と肥料をやったらまた採れた。春夏秋冬二年間も採れ続け、旅行中に実を採らなかったら遂に枯れた。そうか、ナスは夏野菜ではなく、亜熱帯地方の野菜か。それを無理やり日本へ持ってきて育てるから夏にしか生らない。日本で何十世代も品種改良を重ねた種なのに、やっぱりハワイの気候が好きらしい。
日本の農業は亜熱帯のイネを北海道でも育つように品種改良した成功体験がある。ご苦労な事だと思う。ハワイは気候に合った作物を栽培しているだけ。のんびりしたものだ。日本の温室で育てたマンゴーは何千円もするが、ハワイでは道端に落ちている。しかも美味しい。コーヒーも、肥料をやらずに放任しても、土壌と微生物とコーヒーの木のバランスが取れて良いかもしれない。
コロナ禍でも、のんびりした農家暮らしは普段と変わらない。都会の利便性に依存していないから、社会が危機に瀕しても影響は少ない。誠に結構なリタイア生活だ。
と、ここまで言っておきながら、実はコーヒー栽培は、特に収穫作業は、自分が手をかけた分だけ味や質に返って来ることに気が付いた。つい悪い癖で、のめり込んだ。コーヒーの出来不出来が私の工夫と努力を反映している。コーヒーは私を映す鏡だ。それをお客様が喜んでくれればとても嬉しい。サラリーマン生活だと、そうはいかない。組織の歯車として、自分の労働は会社のための労働。会社の商品は自分を実現したものではない。これがマルクスが論じた資本主義の人間疎外か。大学の授業ではピンと来なかったが、農家に転じて、自分なりの合点がいった。農業は人間疎外克服への道。私を投影したコーヒーが私と他者をつなぐ。類的本質なのであーる。なんてね。
農家になって十数年。夢中になってやったら、腰痛が激化した。残念ながら、昨年から大幅に生産量を減らし、自分で消費する分に絞った。スローライフどころか、またもや、弾き飛ばされてしまった。
人生百年時代。さあ、あと四十年間、何しようかなあ。
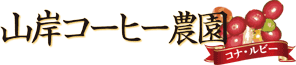


__small.jpg)