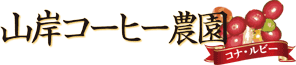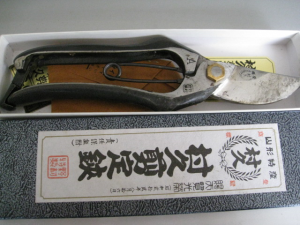SCAA/CQI認定Qグレーダー試験対策(その2)
Sensory Skills Tests 味覚試験
Q Graderの試験の中で最難関の科目といわれる。一発で受かる人は少ないらしい。
甘、塩、酸を識別する味覚の試験。ショ糖、食塩、クエン酸の水溶液が使われる。
それぞれの水溶液が濃いもの、中程度のもの、薄いものの3種類に分かれる。つまり、全部で9種類のカップが用意され、その中身を当てる。ここまでは簡単。(Tests A とTests B)
Test Cが難関。その9種類の水溶液を混合したものが出される。甘、塩、酸の3種類が入っているものが4カップ。2種類だけが入っているものが4カップ。さらに、それぞれ入っているものの強度を当てるというもの。これが非常に難しい。
たとえば、下の表のような答えになる。(当然だが、組み合わえは試験により異なる)
|
|
酸 |
甘 |
塩 |
|
A |
2 |
0 |
1 |
|
B |
2 |
3 |
1 |
|
C |
3 |
1 |
2 |
|
D |
0 |
2 |
1 |
|
E |
1 |
1 |
0 |
|
F |
1 |
2 |
3 |
|
G |
2 |
2 |
0 |
|
H |
1 |
1 |
2 |
| 1薄、2中、3濃 | |||
例えば、塩が入っているのに間違えて0にした場合、あるいは、入っていない(0のところ)に入っていると判断した場合、それぞれ4点マイナス。
さらに、濃度(1,2,3)を間違えると2点マイナスとなる。満点は96点で68点で合格。28点まで間違えても合格できる。制限時間は20分。
酸と甘と塩を組み合わせると、一般的に以下のような濃度の変化を感じると授業で教わった。しかし、テストは20分間と時間が限られているので、そんなことまで考える余裕がなく、全く参考にならなかった。
酸味は甘味を上げる。
塩味は甘味を上げる。
甘味は酸味を下げる。
甘味は塩味を下げる。
酸味は塩味を上げる。
塩味は酸味を下げる。
練習セッションで教官から受けたアドバイスでは、戦略として最初に3つ入っているものと2つしか入っていないものに分けて、それから濃度を考える人が多い。あるいは、甘、塩、酸の濃度3(濃い)ものを最初に見つけて分類していく人もいる。最終的には自分のやりやすい方法で攻めるのがよい。
水溶液の濃度に関しては非公開だが、試験を受けた私の感じでは以下のような具合だった。ただし、混合液の濃度は2つを混合すると半分になるので、2倍の濃度、3つを混合すると3分の1になるので3倍の濃度を使う必要がある。
|
濃 |
中 |
薄 |
|
| クエン酸 |
1/8 |
1/16 |
1/32 |
| 砂糖 |
4 |
2 |
1 |
| 塩 |
1 |
1/2 |
1/4 |
数字は500ccの水に対しての小さじの杯数
スペシャリティーコーヒーの命は酸味と甘み。このテストは酸味を代表するものとして、クエン酸、甘みを代表するものとしてショ糖を使う。塩は何を代表しているのか判らないが、たぶん、それ以外の味覚の代用として使っているのだろう。
教官によれば、味覚は先天的に恵まれた人とそうでない人がいるので、このテストは練習なしでも簡単に受かる人もいれば、いくら頑張ってもダメな人もいるそうだ。
普段からたくさん取りすぎている味覚には鈍感になるので、アメリカ人には甘味で間違える人が多いらしい。私は塩味で間違えた。私は塩が入っているとしょっぱいというよりも美味しいと感じてしまう。
ちなみに、Test AとBで使った、酸、甘、塩、単体の濃中薄の水溶液をTest Cの最中に参考として使えるのかと思っていたら、使えなかった。私はこのテストがそんなに難しいとは知らずに、ろくに練習もせずに行ったら、最初のテストで66点で一つ足りずに落ちた。塩が入っていないものをうまく見つけられずにあたふたしている間に20分が経過してしまった。一つのものにこだわり続けるとダメ。追試を翌日に持ち越すと精神的に参ってしまうので、直後の昼休みに再試験を志願し、今度は80点でクラスで最高得点だった。